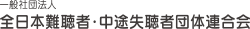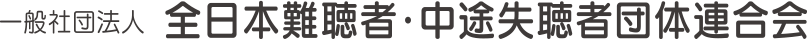2019年2月4日
総務大臣
石田 真敏 殿
字幕電話(文字付電話)実用化に関する検討依頼
一般社団法人
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 新谷友良
本会は、全国の難聴者・中途失聴者に対する施策の充実普及のための諸事業を行い、難聴者等に対する社会の理解を促進させるとともに、難聴者等のコミュニケーション手段等に関する調査研究等を行うことにより、障害者の社会的地位の向上と福祉の増進及び社会参加の促進に寄与することを目的としています。加盟協会は全国55団体で、構成員は約4000名です。
昨年度策定された第4次障害者基本計画においては、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実として、「聴覚障害者向け電話リレーサービスの体制構築」が謳われています。
我が国においては何度かの電話リレーサービスの事業化の試みがあり、現在日本財団が電話リレーサービスを普及・定着させるためにモデルプロジェクトを実施中です。また、全国11の聴覚障害者情報提供施設においても厚生労働省の助成で電話リレーサービス事業が行われています。これらの事業においては、通話にかかる費用は自己負担とされていますが、電話リレーサービスの利用料(通訳料等)は無料とされています。ただ、電話利用者の間に手話通訳、文字入力のための仲介者が必要なシステムのため、利用可能な日や時間に制限があり、24時間・365日、どこでも誰でも利用できる情報インフラとしては不十分な部分があります。
私たち中途失聴・難聴者も多くが現在この電話リレーサービスを利用していますが、電話は声で話し、聞くことで成り立っていますので、タイプ入力のよる会話は不便な面が多くあります。難聴者の場合は、健聴者とほとんど同じように話せる人、発語に困難を抱える人など様々な人がいます。そのような人が音声による入力が出来て、受信は文字と音声で受けるシステムが構築できないか、仲介は技術進歩が著しい音声認識で置換できないか、という問題認識で、今年度私たちは日本財団の助成を受けて「電話利用における音声認識活用」調査事業(添付資料参照)を行っています。この事業においては来年度社会実験を予定し、音声認識技術の実用可能性をさらに検討することとしています。
私たちは今年度の調査事業の中で、電話リレーサービスでの音声認識技術の利用にあたっては、音声認識開発事業者、通信事業者、携帯端末機器開発事業者一体となった取り組みが不可欠であることを痛感しています。音声認識技術を利用した電話リレーサービスは障害者に止まらず、高齢者など社会の各層で利用可能な情報インフラと考えられます。是非、総務省の主導で関係者の知見を集め、音声認識利用による電話リレーサービスの実用化を推進いただきたく、要望いたします。
要望書は中央対策のページにございます
カテゴリー: 要望等
「障害者雇用水増し問題について」要望書を厚労省に提出しました
2019年1月15日
厚生労働大臣
根本 匠 殿
障害者雇用水増し問題について
一般社団法人
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 新谷 友良
障害者雇用を促進するための障害者雇用率制度の運用において、国・地方自治体の障害者雇用数が水増しされていた事態は、多くの障害者の雇用を目指す制度の基礎となる障害者の数を偽っていたものであり、どのような言い訳も許されるものではありません。
我が国の年金も含めた多くの障害者福祉サービスは障害者手帳の保持が条件になっています。しかし、障害者認定の基準は国際的にみて非常に厳しく、聴覚障害を例にとれば、世界保健機関(WHO)報告が人口の6.5%を聴覚障害者としながら、我が国の聴覚の障害者手帳保持者は34万人(人口の0.3%)しかいません。このように、障害者福祉サービスの受給対象者を厳しく制限しながら、制度の目標数字を達成するために障害者の範囲を操作する国の対応は、我が国の障害者施策の根底を揺るがすものと考えます。
民間企業の障害者雇用率は昨年から2.2%となっています。この数字が妥当かどうか様々な議論がありますが、例えばフランスは6%です。しかし、フランスでは障害者雇用における障害の定義が「1つ又は複数の身体・感覚・精神・知的機能を理由とする、障害者がその環境において被る活動の制限または社会生活への参加の制限」とされており、障害者の範囲を広くとらえています。また、障害者の雇用・就労における情報保障の整備など、提供すべき合理的配慮が非常に具体的に規定されています。
「働き方改革」を待つまでもなく、働く意欲のある障害者には広く働く場が与えられなければなりません。多くの障害者の雇用を民間企業や国・自治体で進めていくためには、①障害者雇用における「障害者の範囲」を障害者基本法の定義に沿ったものに改める、②雇用・就労における「合理的配慮の提供」を行政機関等のみならず事業者においても法的義務とするように障害者差別解消法を改正することが求められます。
政府の国会答弁では、このような問題点については「労働政策審議会の障害者雇用分科会においてその在り方を検討する」とされています。しかしながら、障害者雇用分科会の構成は、委員20名中障害者団体の委員は4名であり、また障害者委員には聴覚障害者は含まれていません。このような委員構成で、前述の①、②の問題が十分に検討されるとは到底思えません。
わたしたち、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会はこれら課題について意見を出す場を設けていただきたいと何度か要望いたしましたが、その要望についての真摯な回答をいただいておりません。中途失聴・難聴者の多くは障害者雇用の枠外で就職し、適切な配慮のない状態での就労を強いられております。そして、適切な配慮があれば、その能力を十分に発揮し、社会に対して貢献すると同時に、個人としても生きがいを持って毎日の生活ができます。今回の問題の解決のために、私たちが「障害者雇用分科会」や「国の行政機関における障害者雇用に関するアドバイザー会議」に参加し、意見を出す機会を与えていただくように強く要望いたします。
要望書は中央対策部のページにございます
【声明】障害者雇用水増し問題について
障害者雇用水増し問題について(声明)
2018年9月3日
一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 新谷友良
障害者雇用を促進するための障害者雇用率制度の運用において、国・地方自治体が対象外の職員を障害者の範囲に組み入れて、雇用率を達成したように報告していたことが判明しました。多くの障害者の雇用を目指す制度おいて、その基礎となる障害者の数を偽っていたことは、どのような言い訳も許されるものではありません。
我が国の年金も含めた多くの障害者福祉サービスは障害者手帳の保持が条件になっています。しかし、障害者認定の基準は国際的にみて非常に厳しく、聴覚障害を例にとれば、世界保健機関(WHO)報告が人口の5%を聴覚障害者としながら、我が国の聴覚の障害者手帳保持者は34万人(人口の0.3%)しかいません。このように、障害者福祉サービスの受給対象者を厳しく制限しながら、他方自分たちが作った制度の目標数字を達成するためには平気で障害者の範囲を操作する国の対応は、我が国の障害者施策の根底を揺るがすものと言わざるを得ません。
民間企業の障害者雇用率は今年から2.2%となっています。この数字が妥当かどうか様々な議論がありますが、例えばフランスは6%です。しかし、フランスでは障害者雇用における障害の定義が「1つ又は複数の身体・感覚・精神・知的機能を理由とする、障害者がその環境において被る活動の制限または社会生活への参加の制限」とされており、障害者の範囲を広くとらえています。また、障害者の雇用・就労における情報保障の整備など、提供すべき合理的配慮が非常に具体的に規定されています。
「働き方改革」を待つまでもなく、働く意欲のある障害者には広く働く場が与えられなければなりません。多くの障害者の雇用を民間企業や国・自治体で進めていくためには、
①障害者雇用における「障害者の範囲」を障害者基本法の定義に沿ったものに改める。
②雇用・就労における「合理的配慮の提供」を行政機関等のみならず事業者においても法的義務とするように障害者差別解消法を改正する。
ことが求められます。
「雇用率が達成されれば、障害者雇用の問題が解決」されるという認識が今回の問題を生んでいます。「障害者の範囲」、「合理的配慮の提供」の課題を併せて考えることで、今回の問題を障害者の雇用・就労問題を前進させるきっかけとすることを求めます。
中途失聴・難聴者へのJアラート伝達についての要望
参議院議員に向けての要望
参議院選挙に向けて、中途失聴・難聴者の参政権保障を求める要望書を総務省に提出(2016/6/22)
同要望書提出の経緯は、厚労省、主要活動政党にも報告いたしました。
参議院選挙の要約筆記に関する要望
熊本震災被災障害者への支援に関する緊急要望書提出
日本障害フォーラム(JDF)は、熊本地震に関する省庁緊急要望を内閣総理大臣、厚生労働省、国土交通省あてに行いました。(2016/5/2)
被災障害者への支援に関する緊急要望書