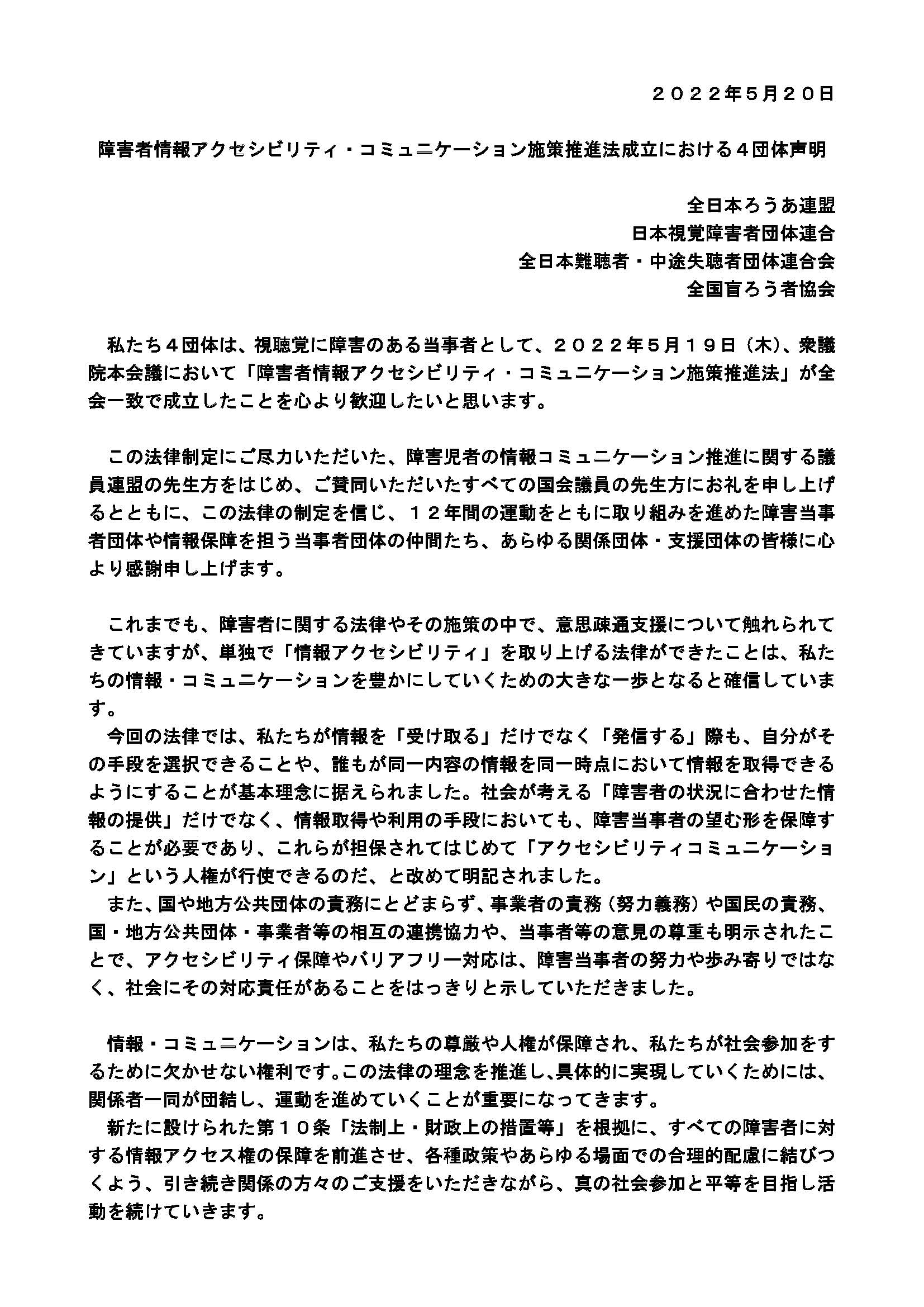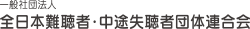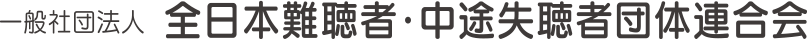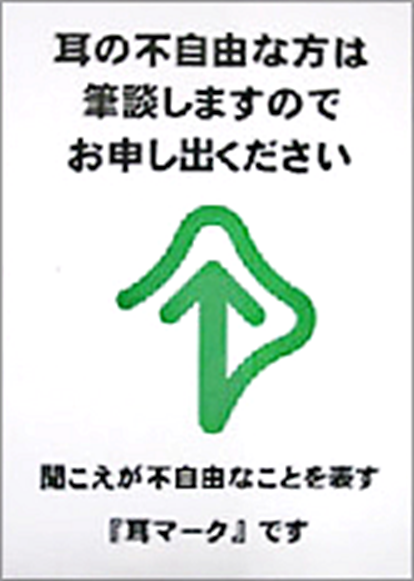当団体は、今回の新型コロナウイルス感染拡大に関する要望を3月25日に発表しましたが、引き続き以下の対策を要望します。
令和2年4月20日
新型コロナウイルスに関する要望 その2(声明)
一般社団法人
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
1.新型コロナウイルス感染問題に関する国・自治体の記者会見などのライブ動画や、その後のアーカイブ動画に字幕を付与すること
政府は4月7日に7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、4月16日に全都道府県を緊急事態措置の対象としました。このような状況で、国や自治体の知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えています。
これらの多くは直接住民の安全に関わる重要な情報ですが、字幕がないと聞こえにくい中途失聴・難聴者には伝わらず、適切な行動をとることができません。都道府県知事の記者会見等のライブ放動画への字幕付与を強く求めます。また、アーカイブの動画には正確な字幕をつけてください。
2.インターネットを利用したテレワーク、遠隔教育、テレビ放送の教材などの音声情報に字幕を付与すること
緊急事態宣言とともに在宅勤務の推進が要請され、インターネットを利用したテレワークやweb会議、eラーニング研修等を行う企業や団体が増えています。
これらインターネットを利用した取り組みにおいては、画像情報に加えて音声情報が大きな役割を担っています。しかし、これらの音声情報に字幕が付与されていなければ、中途失聴・難聴者はその情報を理解できません。これらの取り組みにおいて、字幕の付与、文字入力によるサポート、また事前に書き起こしたテキストを準備するなどの取り組みを強く求めます。
また、中小企業を中心に、テレワークの整備や字幕付与などの体制が整わないために、出勤せざるを得ず、感染のリスクに晒されているケースが多くあります。音声認識技術の活用を含め、字幕付与のシステムの環境整備や相談窓口の設置など、導入にあたっての支援制度の確立を求めます。
一方、教育の場においても、休校措置の拡大で授業や学習教材をネットやテレビで視聴するケースが増えています。聞こえにくい子どもたちには、聞き取りやすい環境や音声情報の可視化(字幕)がなければ、授業・教材の内容が理解できません。子ども向けの教材には必ず字幕をつけ、事前に書き起こしたテキストを渡すなど、子どもの学ぶ環境を守る取り組みを強く求めます。
3.オンライン診療での音声情報の文字化をはじめ、医療場面での情報保障を行うこと
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、初診であってもオンライン診療が受けられることになりました。
オンライン診療においては医療従事者のみならず、患者も一定のITリテラシーが必要になります。しかし、患者は不安感・緊張感のもとにオンライン診療を利用することになり、特に聞こえにくい中途失聴・難聴者は、医師との音声による意思疎通が図れず、オンライン診療にあたっての困難さが倍加します。オンライン診療をスムーズに利用できるよう、診察時の音声情報をすべて文字化するアプリを早急に開発することを要望します。
そして、中途失聴・難聴者もオンライン診療を安心して利用することが出来るよう、診察にあたって、以下のような配慮を是非お願いします。
<意思疎通手段例>
a)マスクは外し、口元をはっきり開けて、ゆっくり話す
b)紙資料を見せる(事前に紙に書いているとスムーズです)
c)筆談したり、コミュニケーション支援ボードを使用する
なお、医療関係団体などによる オンライン診療についての研修を実施する
際には、受講時に中途失聴・難聴者との意思疎通手段や情報保障について周知
してください。
また、病院や医師への問い合わせ手段が電話のみの場合、不急であっても
病院に行くことが必要になります。感染のリスクを高めないよう、FAXやメ
ールなどで連絡できるようにしてください。
(参考)オンライン診療の適切な実施に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000201789.pdf
中途失聴・難聴者に対する合理的配慮等具体例として、下記のサイトもご参照ください。
(参考)合理的配慮等具体例データ集(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_choukaku.html
(声明についての問い合わせ先)
一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町14-5 MSビル市ヶ谷台1F
電話: 03-3225-5600 FAX: 03-3354-0046
全難聴声明「新型コロナウイルスに関する要望その2」